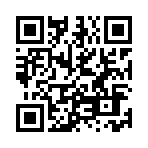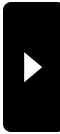2008年11月18日
中学生チャレンジウィーク
介護施設と地域とのつながりは非常に重要である。
「介護・福祉」分野への地域住民への理解を深めていただく為にも、機会あるごとに外部の人を受け入れていきたいと思っている。
と、言う訳で今年度「中学生チャレンジウィーク」で地元高月中学校の2年生を受け入れる事にした。
「中学校チャレンジウィーク」とは…
滋賀県教育委員会が作成したチラシによると、
◎趣旨
中学校2年生において5日間以上の職場体験を実施し、働く大人の生きざまに触れたり、自分の生き方を考えたりする機会とし、自分の進路を選択できる力や将来社会人として自立できる力を育てる。
◎なぜ5日間なのか
・1日や2日では、互いによそよそしくてお客さん扱いで終わる。(仕事を覚えることに精いっぱい)
・3日目で気持ちに変化が出てくる。(仕事に慣れるとともにつらさを感じる)
・4日目で仕事に自分らしさが出せる。(創意工夫や自分なりの努力)
・5日目で、成就感を得られる。(職場の方との人間関係の深化と感動体験)
・5日間の体験を終えた生徒のうち9割が「充実していた」と答えている。
◎目的
・中学校2年生に将来の自分の生き方について考える機会をつくり、自分の進路を選択できる力や将来社会人として自立できる力を育てる
・働く大人の生きざまに触れる
・地域の子供を地域で育てていく
とある。
また別頁には、「社会での自立を目指した滋賀のキャリア教育」としてステップアップ図が示されている。
小学校においては、「大人の生き方を知る」 「将来の夢を持つ」 「社会について学ぶ」事を柱とし、
中学校においては、「進路選択(目的意識を持つ)」事をテーマに、「自分の生き方を考え、働く大人の姿に学ぶ」経験として「中学生チャレンジウィーク」があり、
高等学校においては、実社会での体験などを通じて、「自己の生き方・在り方を考え」、社会での自立(就職)へとつなげていく、というものだ。文部科学省も推進しているそうだ。
さて、その実際なのだが…
「来年からの受け入れは再検討だな…」というのが正直な感想である。
まず、事前の受け入れ側と依頼側(学校)の打ち合わせが全くなかった。先生方も忙しいのだろうが、忙しいのはこちらとて同じである。事前に受け入れの有無を確認する文書が来ただけで、後は生徒が事前訪問にやってきて簡単な打ち合わせをするだけである。
どういう「ねらい」でこの実習を行うのか、学校と職場には共通認識がなく、意思の疎通もなく、受け入れ側に丸投げ状態である。そして後は生徒の自主性が頼り。
生徒は生徒で、必ずしも自ら希望した「職場」に配属されるとは限らず、不本意ながら来たという生徒もいる。そういう生徒はあから様に表情に出るからすぐわかる。
それでも事前に自分が配属される職場はどのような仕事をしているのかぐらい事前学習していてもよさそうなものだ。
こっちもヒマで付き合っているのではないのだから。
期間中先生は巡回で2回来たのみ、しかも向こうの都合で現れたので、白うさぎも業務中で全く話ができなかった。
このような状態で「なんでもさせてあげて下さい」と言われても
「無理ですっ!」
中途半端な状態で放り込まれる生徒もかわいそうといえばかわいそうなのだが…。
慣れてきて、ちょっとだらけた感じでいる姿を目撃し、すかさず注意したのだが、スタッフの子らは「最近の中学生ってあんなもんでしょ」と言う。
白うさぎも大分丸くなったから、「君らレストランに行って店員がだらけていて注文も聞きに来なかったらどうする?ここの利用者さんもお金を払って来ているのだから、きちんとしたサービスを受ける権利があるんだ。だからスタッフはきちんとした対応しないといけないんだぞ!」などと言っておいたが、数年前なら「ヤル気がないなら帰れっ!」と言ってるよなぁ…昔居眠りしていた実習生を一喝した事もあるしさ。でも、やっぱり白うさぎとしては、「最近の中学生もヤルやん!」と思わせて欲しかったな。残念だ。
白うさぎが中学時代にはもちろんこのようなプログラムがなかったし、まだ真剣に「働く」という事を意識していなかった。だから実際にこういう機会があってもきちんと動けていたかどうかは疑問だ。
だけど昔の様に当たり前の様に家業を継ぐという子供は減って、サラリーマンになる子供が増えているこの時代だからこそ、この様な取り組みが必要な訳だし、事前に生徒に対してしっかり教育しておいて欲しいと思う。
生徒へのコメントには、
「チャレンジできたのか思い返しそう」
「チャレンジとはベストを尽くしたかどうか」
「ベストとは特別な事でなく自分のできるだけの事、例えば大きな声で挨拶する、実習簿を毎日書く、笑顔…」
等書いた。少しでもこれからの人生においてプラスになる事を祈ってやまない。
「中学生チャレンジウィーク」(滋賀県教育委員会)PDFファイル
「介護・福祉」分野への地域住民への理解を深めていただく為にも、機会あるごとに外部の人を受け入れていきたいと思っている。
と、言う訳で今年度「中学生チャレンジウィーク」で地元高月中学校の2年生を受け入れる事にした。
「中学校チャレンジウィーク」とは…
滋賀県教育委員会が作成したチラシによると、
◎趣旨
中学校2年生において5日間以上の職場体験を実施し、働く大人の生きざまに触れたり、自分の生き方を考えたりする機会とし、自分の進路を選択できる力や将来社会人として自立できる力を育てる。
◎なぜ5日間なのか
・1日や2日では、互いによそよそしくてお客さん扱いで終わる。(仕事を覚えることに精いっぱい)
・3日目で気持ちに変化が出てくる。(仕事に慣れるとともにつらさを感じる)
・4日目で仕事に自分らしさが出せる。(創意工夫や自分なりの努力)
・5日目で、成就感を得られる。(職場の方との人間関係の深化と感動体験)
・5日間の体験を終えた生徒のうち9割が「充実していた」と答えている。
◎目的
・中学校2年生に将来の自分の生き方について考える機会をつくり、自分の進路を選択できる力や将来社会人として自立できる力を育てる
・働く大人の生きざまに触れる
・地域の子供を地域で育てていく
とある。
また別頁には、「社会での自立を目指した滋賀のキャリア教育」としてステップアップ図が示されている。
小学校においては、「大人の生き方を知る」 「将来の夢を持つ」 「社会について学ぶ」事を柱とし、
中学校においては、「進路選択(目的意識を持つ)」事をテーマに、「自分の生き方を考え、働く大人の姿に学ぶ」経験として「中学生チャレンジウィーク」があり、
高等学校においては、実社会での体験などを通じて、「自己の生き方・在り方を考え」、社会での自立(就職)へとつなげていく、というものだ。文部科学省も推進しているそうだ。
さて、その実際なのだが…
「来年からの受け入れは再検討だな…」というのが正直な感想である。
まず、事前の受け入れ側と依頼側(学校)の打ち合わせが全くなかった。先生方も忙しいのだろうが、忙しいのはこちらとて同じである。事前に受け入れの有無を確認する文書が来ただけで、後は生徒が事前訪問にやってきて簡単な打ち合わせをするだけである。
どういう「ねらい」でこの実習を行うのか、学校と職場には共通認識がなく、意思の疎通もなく、受け入れ側に丸投げ状態である。そして後は生徒の自主性が頼り。
生徒は生徒で、必ずしも自ら希望した「職場」に配属されるとは限らず、不本意ながら来たという生徒もいる。そういう生徒はあから様に表情に出るからすぐわかる。
それでも事前に自分が配属される職場はどのような仕事をしているのかぐらい事前学習していてもよさそうなものだ。
こっちもヒマで付き合っているのではないのだから。
期間中先生は巡回で2回来たのみ、しかも向こうの都合で現れたので、白うさぎも業務中で全く話ができなかった。
このような状態で「なんでもさせてあげて下さい」と言われても
「無理ですっ!」
中途半端な状態で放り込まれる生徒もかわいそうといえばかわいそうなのだが…。
慣れてきて、ちょっとだらけた感じでいる姿を目撃し、すかさず注意したのだが、スタッフの子らは「最近の中学生ってあんなもんでしょ」と言う。
白うさぎも大分丸くなったから、「君らレストランに行って店員がだらけていて注文も聞きに来なかったらどうする?ここの利用者さんもお金を払って来ているのだから、きちんとしたサービスを受ける権利があるんだ。だからスタッフはきちんとした対応しないといけないんだぞ!」などと言っておいたが、数年前なら「ヤル気がないなら帰れっ!」と言ってるよなぁ…昔居眠りしていた実習生を一喝した事もあるしさ。でも、やっぱり白うさぎとしては、「最近の中学生もヤルやん!」と思わせて欲しかったな。残念だ。
白うさぎが中学時代にはもちろんこのようなプログラムがなかったし、まだ真剣に「働く」という事を意識していなかった。だから実際にこういう機会があってもきちんと動けていたかどうかは疑問だ。
だけど昔の様に当たり前の様に家業を継ぐという子供は減って、サラリーマンになる子供が増えているこの時代だからこそ、この様な取り組みが必要な訳だし、事前に生徒に対してしっかり教育しておいて欲しいと思う。
生徒へのコメントには、
「チャレンジできたのか思い返しそう」
「チャレンジとはベストを尽くしたかどうか」
「ベストとは特別な事でなく自分のできるだけの事、例えば大きな声で挨拶する、実習簿を毎日書く、笑顔…」
等書いた。少しでもこれからの人生においてプラスになる事を祈ってやまない。
「中学生チャレンジウィーク」(滋賀県教育委員会)PDFファイル
Posted by 白うさぎ at 23:58│Comments(0)
│『おたっしゃ倶楽部』日誌