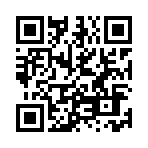› “帰ってきた”おたっしゃな日々… › 飛び出し坊や
› “帰ってきた”おたっしゃな日々… › 飛び出し坊や2007年10月14日
「飛び出し坊や」その4
運動会に行ったついでに、集落内の「飛び出し坊や」を採集してみた。

図6:湖北町速水にて採取。(規格品であり、ホームセンターで売っているものである。)

図7:湖北町速水にて採取。(女の子だが、このタイプは初めて見かける。小学校の金網に取り付けてあり、通学路の注意を喚起するものであろう。)
図6:湖北町速水にて採取。(規格品であり、ホームセンターで売っているものである。)
図7:湖北町速水にて採取。(女の子だが、このタイプは初めて見かける。小学校の金網に取り付けてあり、通学路の注意を喚起するものであろう。)
タグ :飛び出し坊や
2007年08月25日
「飛び出し坊や」その3
今日は福祉ゾーンと柏原区の月例会議があったので行ってきた。
そしたら柏原区内でまた「飛び出し坊や」看板を発見した。
図3:高月町柏原で採取。(黄色い旗を持って道路を横断しようとしている子供の後ろには横断歩道を示す道路標識が…。一時停止の標識が設置されてるのは、走ってくる車側なのか、子供が渡ろうとする前方なのか不明だが、いずれにしても子供側に非があるようには見えず、「飛び出し坊や」ではなく、「飛び出してくる危険運転の車」に対して注意を促す看板なのだろうか?)
図4:高月町柏原で採取。(これも高月町社会福祉協議会が設置した看板の様だが、かなり年季が入っている看板。服装に時代を感じる。)
図5:高月町柏原で採取。図4の隣に設置してあった。(驚き顔のみだが、妙にインパクトがある。ここは飛び出し多発地帯なのか )
)
2007年08月22日
「飛び出し坊や」ふたたび…
毎日自転車通勤していて気が付いたことが…。
国道8号線沿いには「彼ら」の姿がほとんど見られないことだった。
自宅から会社までの間でたった一つしか設置されていなかった。近江八幡市で働いている頃は、もっとたくさん見かけたものだが…。
ちなみに8号線から一歩街中へ入ると、いるわ、いるわ…。
実際問題、「飛び出し坊や」が注意を喚起するのが目的なら、国道の方が危ないような気がするのだが…。

図2:高月町柏原にて採取。(高月町社会福祉協議会が設置したものらしく、町内各所に設置されている。全て同じなので、ちょっと味気ない。)
国道8号線沿いには「彼ら」の姿がほとんど見られないことだった。
自宅から会社までの間でたった一つしか設置されていなかった。近江八幡市で働いている頃は、もっとたくさん見かけたものだが…。
ちなみに8号線から一歩街中へ入ると、いるわ、いるわ…。
実際問題、「飛び出し坊や」が注意を喚起するのが目的なら、国道の方が危ないような気がするのだが…。
図2:高月町柏原にて採取。(高月町社会福祉協議会が設置したものらしく、町内各所に設置されている。全て同じなので、ちょっと味気ない。)
2007年08月13日
飛び出し坊や
白うさぎの隠れ趣味に「飛び出し坊や」探しがある。
滋賀県民の皆さんはよーくご存知だと思うが、ここで一応「飛び出し坊や」の定義を述べる。
『飛び出し坊や(とびだしぼうや)とは、主に児童への交通安全の呼びかけのために、通学路などに設置されている看板のことである。なお、正式な名称は存在せず、「飛び出し小僧」とも呼ばれる。』
出典:フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」
「飛び出し坊や研究」の第一人者は、みうらじゅん氏だが、氏によれば、この滋賀県は「飛び出し坊や」の多発地帯だということだ。そもそも「飛び出し坊や」は関西圏を中心に広く分布しているらしいが、その数が滋賀県はダントツに多い(ようだ…正確な統計に基づいていないので)。もしかしたら滋賀県は発祥の地かもしれない?(実際のところどこが発祥かは明らかになっていない。)
さて、この研究何が面白いかと言えば、その数もさることながら、バリエーションの豊富さが挙げられよう。
その多くが手作りによるもので、形の変化によって伝播の過程が垣間見えたりして興味深い。
一般的に物事は「噂話」などでもそうだが、伝わっていく過程で省略されたり、尾ひれが付いていったりするものである。
「飛び出し坊や」も実はプロトタイプ(原型)が存在し、複数の手により模写される内に段々その姿が変化していき、さらに地域ごとに独自のアレンジが加えられたりして現在に至るのではないか?という仮説が成立する。
白うさぎもみうらじゅん氏にインスパイアされたという訳でもないのだが、根っからのフィールドワーク好きなもので、実際に注意して見ていくと確かに様々な「飛び出し坊や」が散見され興味深い。
形が不揃いな証拠として「小学校の頃、みんなで作った」という証言が得られたり、甲賀市内には忍者バージョンの「飛び出し坊や」が存在したり、「飛び出し坊や」といえば基本的には男の子なのだが、まれに女の子バージョンも存在するなどなど。
そして滋賀県民にとってはなじみ深い存在であるこの「飛び出し坊や」も、実は他県の者にとっては意外とマイナーな存在だったりする事実
白うさぎの妹は奈良県に住んでいるが、みうらじゅんの本を読んで、「滋賀は“飛び出し坊や”のメッカ」だと知り、実際に見てとても感激していた
滋賀県を出るとそれ程「飛び出し坊や」の数は激減するのだ。この話を滋賀県民にすると「うそっ どこにでもあるもんじゃないの
どこにでもあるもんじゃないの 」と一様に驚いていた。
」と一様に驚いていた。
この「飛び出し坊や」も最近はホームセンターなどで売られているカワイイもののこれといった特徴のないものに取って代わられだしている。これは一大事である
この失われゆく手作りの「飛び出し坊や」の姿をちょくちょくアップしていきたい。

図1:米原市下丹生にて採取。(帽子の「S」は醒井小学校の「S」か?黄色い帽子・赤いシャツ・青いズボンという三色の取り合わせは「飛び出し坊や」によく見られる類型である。帽子の形が微妙…野球帽にも見えるが… )
)
滋賀県民の皆さんはよーくご存知だと思うが、ここで一応「飛び出し坊や」の定義を述べる。
『飛び出し坊や(とびだしぼうや)とは、主に児童への交通安全の呼びかけのために、通学路などに設置されている看板のことである。なお、正式な名称は存在せず、「飛び出し小僧」とも呼ばれる。』
出典:フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」
「飛び出し坊や研究」の第一人者は、みうらじゅん氏だが、氏によれば、この滋賀県は「飛び出し坊や」の多発地帯だということだ。そもそも「飛び出し坊や」は関西圏を中心に広く分布しているらしいが、その数が滋賀県はダントツに多い(ようだ…正確な統計に基づいていないので)。もしかしたら滋賀県は発祥の地かもしれない?(実際のところどこが発祥かは明らかになっていない。)
さて、この研究何が面白いかと言えば、その数もさることながら、バリエーションの豊富さが挙げられよう。
その多くが手作りによるもので、形の変化によって伝播の過程が垣間見えたりして興味深い。
一般的に物事は「噂話」などでもそうだが、伝わっていく過程で省略されたり、尾ひれが付いていったりするものである。
「飛び出し坊や」も実はプロトタイプ(原型)が存在し、複数の手により模写される内に段々その姿が変化していき、さらに地域ごとに独自のアレンジが加えられたりして現在に至るのではないか?という仮説が成立する。
白うさぎもみうらじゅん氏にインスパイアされたという訳でもないのだが、根っからのフィールドワーク好きなもので、実際に注意して見ていくと確かに様々な「飛び出し坊や」が散見され興味深い。
形が不揃いな証拠として「小学校の頃、みんなで作った」という証言が得られたり、甲賀市内には忍者バージョンの「飛び出し坊や」が存在したり、「飛び出し坊や」といえば基本的には男の子なのだが、まれに女の子バージョンも存在するなどなど。
そして滋賀県民にとってはなじみ深い存在であるこの「飛び出し坊や」も、実は他県の者にとっては意外とマイナーな存在だったりする事実

白うさぎの妹は奈良県に住んでいるが、みうらじゅんの本を読んで、「滋賀は“飛び出し坊や”のメッカ」だと知り、実際に見てとても感激していた

滋賀県を出るとそれ程「飛び出し坊や」の数は激減するのだ。この話を滋賀県民にすると「うそっ
 どこにでもあるもんじゃないの
どこにでもあるもんじゃないの 」と一様に驚いていた。
」と一様に驚いていた。この「飛び出し坊や」も最近はホームセンターなどで売られているカワイイもののこれといった特徴のないものに取って代わられだしている。これは一大事である

この失われゆく手作りの「飛び出し坊や」の姿をちょくちょくアップしていきたい。
図1:米原市下丹生にて採取。(帽子の「S」は醒井小学校の「S」か?黄色い帽子・赤いシャツ・青いズボンという三色の取り合わせは「飛び出し坊や」によく見られる類型である。帽子の形が微妙…野球帽にも見えるが…
 )
)