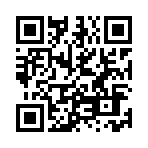› “帰ってきた”おたっしゃな日々… › 歴史
› “帰ってきた”おたっしゃな日々… › 歴史2007年07月27日
「野神さん」と「高月」の地名の由来
白うさぎのデイサービスセンターは国道365号線沿いにある。このルートは旧北国脇往還である。戦国時代、豊臣秀吉が羽柴秀吉だった頃、柴田勝家との賤ヶ岳の合戦において、大垣からわずか5時間で木之本まで取って返したという、いわゆる「美濃大返し」のルートでもある。
歴史好きな白うさぎは何度かこのルートを車で走ってみたが、大垣→垂井→関ヶ原→玉→藤川→春照→伊部→郡上→木之本とずっとのぼりが続くルートで、「こんなところをよくもまあ」と感嘆せずにいられない。足軽たちは完全武装のまま、途中村人が炊き出した握り飯を頬張りながら、村人が照らす松明の灯りの中駆け続けたという。(ス、スゴイ!!)
一説によると足軽たちは軽装で、武具はまた別に運んだのではないか?とも言われている。その他に行く先々の食料等の手配をしたのが石田佐吉、すなわち石田三成だったのではないか?とも言われている。(石田三成は「しまさこにゃん」のモデル島左近勝猛のご主人様だ)
さて話がそれてしまったが、そんな歴史と関係の深いこの土地に「野神さん」と呼ばれる立派な欅(けやき)の大木がある。白うさぎのデイサービスセンターとは国道を挟んで向かい側だ。
湖北地方のあちこちには、「野神」または「野大神」と呼ばれている巨木(欅だったり杉だったり種類は色々ある)が見られ、五穀豊穣の神として古くから地域の人々から崇められている。
この柏原区八幡神社の野神さん以外にも立派な欅は高月町内によく見られる。
この欅については、古くは「槻(ツキ、ツキノキ)」ともいっていて、「高月」は、元々は「高槻」だったということだ。それが平安時代の歌人、大江匡房が、名月を愛でながら歌を詠んだことにちなみ「高月」と呼ぶようになったというから、「高月」という地名は大変美しい由緒を持った地名であるということがわかる。
少し前に大阪府のJR高槻駅と紛らわしいので、JR高月駅の駅名を変更するという話があったのだが、「こんな美しい名前なのになんてもったいない!」と思ったものである。(幸い名称はそのままとなった。)
歴史好きな白うさぎは何度かこのルートを車で走ってみたが、大垣→垂井→関ヶ原→玉→藤川→春照→伊部→郡上→木之本とずっとのぼりが続くルートで、「こんなところをよくもまあ」と感嘆せずにいられない。足軽たちは完全武装のまま、途中村人が炊き出した握り飯を頬張りながら、村人が照らす松明の灯りの中駆け続けたという。(ス、スゴイ!!)
一説によると足軽たちは軽装で、武具はまた別に運んだのではないか?とも言われている。その他に行く先々の食料等の手配をしたのが石田佐吉、すなわち石田三成だったのではないか?とも言われている。(石田三成は「しまさこにゃん」のモデル島左近勝猛のご主人様だ)
さて話がそれてしまったが、そんな歴史と関係の深いこの土地に「野神さん」と呼ばれる立派な欅(けやき)の大木がある。白うさぎのデイサービスセンターとは国道を挟んで向かい側だ。
湖北地方のあちこちには、「野神」または「野大神」と呼ばれている巨木(欅だったり杉だったり種類は色々ある)が見られ、五穀豊穣の神として古くから地域の人々から崇められている。
この柏原区八幡神社の野神さん以外にも立派な欅は高月町内によく見られる。
この欅については、古くは「槻(ツキ、ツキノキ)」ともいっていて、「高月」は、元々は「高槻」だったということだ。それが平安時代の歌人、大江匡房が、名月を愛でながら歌を詠んだことにちなみ「高月」と呼ぶようになったというから、「高月」という地名は大変美しい由緒を持った地名であるということがわかる。
少し前に大阪府のJR高槻駅と紛らわしいので、JR高月駅の駅名を変更するという話があったのだが、「こんな美しい名前なのになんてもったいない!」と思ったものである。(幸い名称はそのままとなった。)